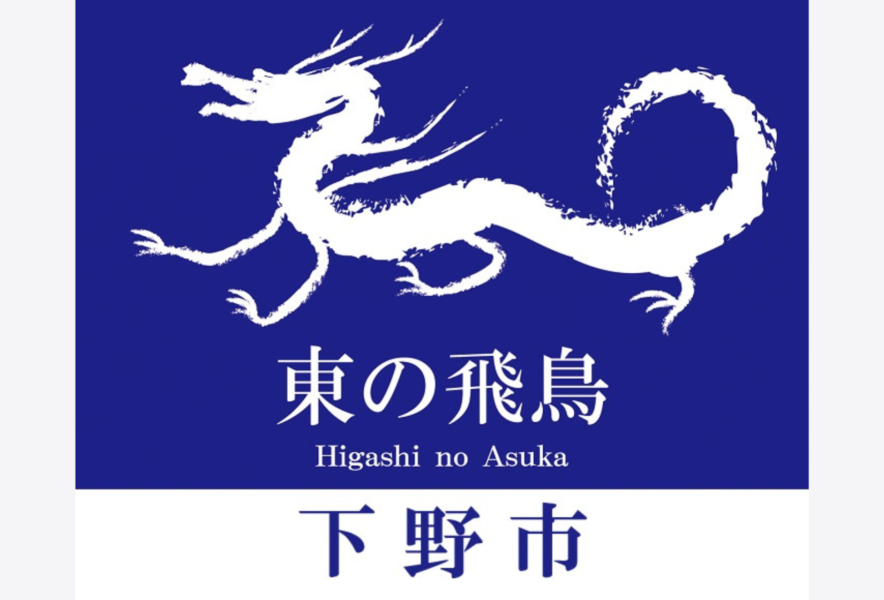栃木県南部にある下野(しもつけ)市には、栃木県初の国指定史跡「下野薬師寺跡」や「下野国分寺・国分尼寺跡」をはじめ、東国(とうごく)を代表する重要な史跡が集中している地域だ。これらの史跡からは古墳時代から飛鳥・奈良時代への変遷をうかがえ、「日本」という国が成立した7世紀に都がおかれた古代文化発祥の地・奈良県飛鳥地方と共通している。この歴史的特性を下野市では「東の飛鳥」と名付け、文化財の保存活用に取り組んでいる。この記事では、下野市にある2つの資料館「しもつけ風土記の丘資料館」と「下野薬師寺歴史館」を中心に、周辺の史跡と古墳を巡るコースを紹介する。
協力◉下野市
【しもつけ風土記の丘資料館周辺エリア】
古墳時代から奈良時代までの歴史を学べる「しもつけ風土記の丘資料館」
解説パネルや映像、貴重な資料を通して、古墳時代から奈良時代頃までの下野市の歴史に触れられる資料館。歴史を初めて学ぶ小学生はもちろん、大人にとっても分かりやすい内容になっている。館内は古墳時代・飛鳥時代・奈良時代の歴史を紹介する各エリアと企画展示エリアの4つで構成され、資料館からほど近い「甲塚(かぶとづか)古墳」から出土した国指定重要文化財の数々が見どころだ。

【しもつけ風土記の丘資料館】
所在地:栃木県下野市国分寺993
電話:0285-44-5049
開館時間:午前9時から午後5時まで(入館は午後4時30分まで)
休館日:毎週月曜日(休日の場合はその翌日)、第3火曜日(休日の場合は除く)、休日の翌日(土・日曜日、休日の場合は除く)、年末年始(12月28日から1月4日まで)
入館料:無料
6世紀後半に作られた帆立貝形前方後円墳「甲塚古墳」
全長約80mの帆立貝形前方後円墳である甲塚古墳は「しもつけ風土記の丘資料館」の西側に位置する。発掘調査によって、平坦な墳丘第1段目に円筒埴輪列が、前方部西側部分には前述の機織形埴輪や馬形埴輪などの形象埴輪が並べられていることがわかった。その近くには大量の土器などが並べられていたことも分かっており、出土遺物などから6世紀後半に造られたと考えられている。

広大な公園として整備された「国指定史跡 下野国分寺・国分尼寺跡」
天平13(741)年に発せられた聖武天皇の「国分寺建立の詔」によって、全国に良い場所を選んで国分寺と国分尼寺が建てられた。下野市域は古来より高低差があまりなく、開けていて安定した自然災害の少ない地域であったため、下野国分寺・国分尼寺建立の地に選ばれた。ここでは、国家の平和を祈るための儀式が執り行われたという。周辺には現在も「国分寺」の地名が残る。2つの史跡周辺は天平の丘公園として整備が行われ、県内有数の桜の名所としても知られている。敷地内の「しもつけ風土記の丘資料館」とあわせての散策がおすすめだ。


ちょっと一息!シェアスぺース「夜明け前」(国登録有形文化財 旧山中家住宅)
「天平の丘公園」の散策中にちょっと一息をつきたいときは、国登録有形文化財の旧山中家住宅で営業されているシェアスぺース「夜明け前」がおすすめ。旧山中家住宅は江戸末期に建築されたと伝わる主屋を移築したもので、土間が広く、部屋の周りに縁が巡る大規模な配置となっている。この地域を代表する貴重な農家建築だ。現在は古民家カフェとして、また、様々なグループ活動等の場として活用されている。隣接する売店「10picnic tables(テンピクニックテーブルス)」で購入した飲食物を、「夜明け前」に持ち込んで食べるのもよし。窓辺を彩る四季折々の自然を眺めながら、ゆっくりとした時間を過ごしてみてはいかがだろう。

【10picnic tables/古民家カフェ「夜明け前」】
所在地:天平の丘公園(下野市国分寺821-1)
※ナビ検索の場合は、「下野市国分寺993-1(しもつけ風土記の丘資料館)」が便利
開館時間:午前11時から午後5時まで
定休日:毎週月曜日、毎月第3火曜日、年末年始
7世紀初め頃の円墳「丸塚古墳」
「下野国分寺・国分尼寺跡」の北に位置する栃木県指定史跡の「丸塚古墳」。直径約66m、高さが約7mの二段に造られた円墳だ。墳丘の南側に造られた横穴式石室は、側壁・奥壁・天井石ともの巨大な一枚石により構成され、石室の入口は一枚石の中央をくり抜いた「刳(く)り抜き玄門(げんもん)」と呼ばれる技法を用いて作られている。埴輪のない円墳であることから、7世紀初めごろに造られたと考えられている。

【下野薬師寺歴史館周辺エリア】
展望デッキからの眺望も見逃せない「下野薬師寺歴史館」
「国指定史跡 下野薬師寺跡」の南西に隣接した下野薬師寺のガイダンス施設。発掘調査で見つかった瓦をはじめとする出土遺物、下野薬師寺に関る文献史料、復元模型などの展示のほか、映像などによって下野薬師寺の歴史をわかりやすく解説してくれている。屋上の展望デッキからは下野薬師寺跡を一望できるほか、筑波山や日光連山、遠くは那須の山々、冬の空気の澄んだ晴れた日には富士山まで、関東平野を360度眺めることができる。

【下野薬師寺歴史館】
所在地:栃木県下野市薬師寺1636
電話:0285-47-3121
開館時間:午前9時から午後5時まで(入館は午後4時30分まで)
休館日:毎週月曜日(休日の場合はその翌日)、第3火曜日(休日の場合は除く)、休日の翌日(土・日曜日、休日の場合は除く)、年末年始(12月28日から1月4日まで)
入館料:無料
日本三戒壇として名高い「国指定史跡 下野薬師寺跡」
下野薬師寺は7世紀末ごろに建立されたと考えられる寺院。奈良時代後半の8世紀中頃に僧の資格を得るための場である「戒壇」が設置されたことから、東大寺(奈良県)や筑紫観世音寺(福岡県)とともに日本三戒壇のひとつと呼ばれている。下野薬師寺で受戒した僧は、東国各地の国分寺などに派遣されていた。東国随一の寺として隆盛し、その姿は都の寺院に並ぶほどであったと伝えられている。また、道鏡が晩年を過ごした場所としても有名だ。周辺には現在も「薬師寺」の地名が残る。跡地には回廊の一部が再現され、毎年3月上旬の梅の花が見頃を迎えるころには梅まつりが開催される。

しもつけ古墳群の一つ、前方後円墳「御鷲山古墳」
下野薬師寺跡から北に約150mに位置する、全長約74mの前方後円墳。全長約12mの石室からは馬具や武器、武具類が出土しているほか、墳丘からは円筒埴輪や朝顔形埴輪、須恵器の破片が確認されている。6世紀の後半に築造されたと考えられる。御鷲山古墳を含むおよそ10km四方の地域は、古墳時代後期の首長墓で構成される「しもつけ古墳群」が分布し、住宅や田畑の間に突如として現れるいにしえの痕跡を垣間見ることができる。また、前方後円墳の場合、本来は後円部に埋葬施設を造るが、しもつけ古墳群においては前方部に埋葬施設をもつという特徴がある。