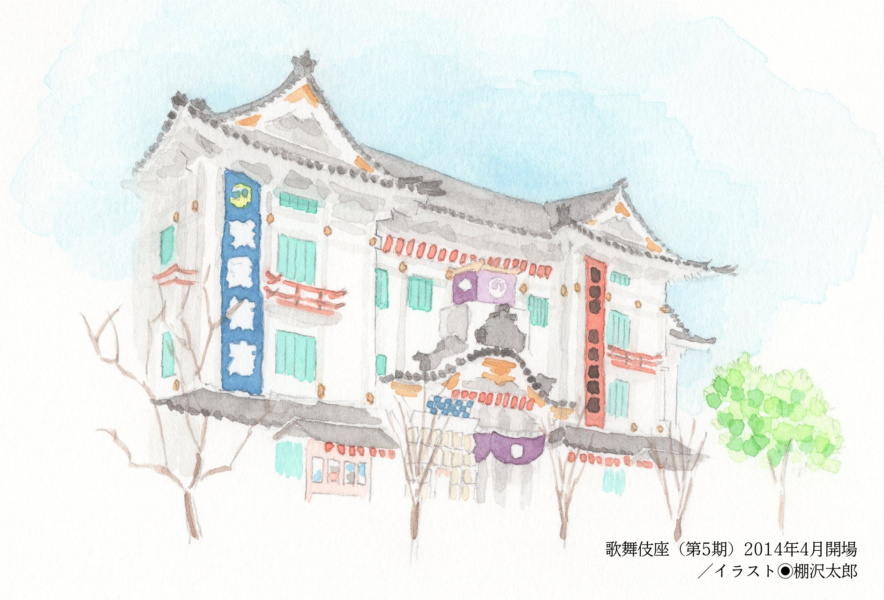雑誌『一個人』2024年7月号の連載記事を本サイトにも掲載しております。内容は雑誌発行当時のものです。
執筆◉宗教学者・作家 島田裕巳、イラスト◉棚沢太郎
もし今月、2024年6月から歌舞伎座ではじめて歌舞伎を観みるという人がいたとしたら、その人はとても幸運だ。なにしろ、六代目中村時蔵(ときぞう)と初代中村萬壽(まんじゅ)などの襲名披露狂言を観ることができるからだ。
襲名は、他の伝統芸能でも行われている。落語でも襲名はある。だが、歌舞伎ほど華やかに襲名披露を行う芸能はない。
2022年には、十三代目市川團十郎白猿(だんじゅうろうはくえん)の襲名披露が歌舞伎座で行われたが、それは11月と12月の2カ月に及んだ。コロナの流行で延期されたもので、本来は3カ月の興行が予定されていた。歌舞伎のことが世間をにぎわすのも襲名披露のときである。
一般の芸能人でも芸名を名乗る。歌舞伎役者も芸名だが、その特徴は、それぞれの家で代々名前を受け継いでいくことにある。だから、團十郎の場合には十三代目となるわけである。初代は江戸時代初期だ。
しかも、一人の役者が襲名をくり返すことも珍しくない。團十郎の場合だと、初舞台で新之助(しんのすけ)を名乗り、2004年に海老蔵(えびぞう)を襲名した。團十郎家の屋号が成田屋(なりたや)になるが、どちらも成田屋で代々受け継がれてきた名前で、新之助としては七代目、海老蔵としては十一代目だった。
歌舞伎の世界では、襲名し、名前を受け継ぐことは、芸を受け継ぐことでもある。成田屋には、「勧進帳(かんじんちょう)」や「助六(すけろく)」といった歌舞伎十八番が伝えられている。襲名したら、そうした演目を立派にやりとげられるだけの役者に成長していかなければならないのだ。
襲名は、本人にとってとても名誉なことである一方、相当なプレッシャーでもある。そのプレッシャーという試練を克服できると見なされないと、襲名を許されない。襲名は、歌舞伎役者にとってもっとも重要な「通過儀礼」(※)なのだ。
※)通過儀礼…人々の生涯における誕生・成人・結婚・死亡といった節目を通過する際に行なわれる儀礼のこと。成人式では、生と死が隣り合わせである祭礼を行ない、社会的に一人前として認められる。
襲名という仕組みがあるからこそ、歌舞伎は現代でも隆盛を誇っている。そして、襲名披露があれば、多くの観客が劇場を訪れる。とくに初日は格別で、観客の期待度も大きく、盛大な拍手が送られる。
今回襲名する時蔵の前名は梅枝(ばいし)で、その名は新時蔵の息子に受け継がれる。その代わり、現在の時蔵は、これまでなかった萬壽を襲名する。こうしたこともある。
新時蔵の舞台はいろいろと観てきたが、昨年の後半から進境著しいものがあった。女形(おんながた)として花が開いてきた。観劇して、そう思うことが少なくなかった。それも、襲名が決まり、覚悟が決まったからだろう。
襲名披露に接すれば、観客も、その舞台を忘れられなくなる。襲名の際にはそのための口上(こうじょう)が行われるが、襲名した役者の挨拶のときの晴れがましい表情は強く印象に残る。
だからこそ、初めての歌舞伎が襲名披露だというのはとても幸運なことなのだ。襲名披露はあっても年に一度くらいだ。
今、歌舞伎座に急いだ方がいい。